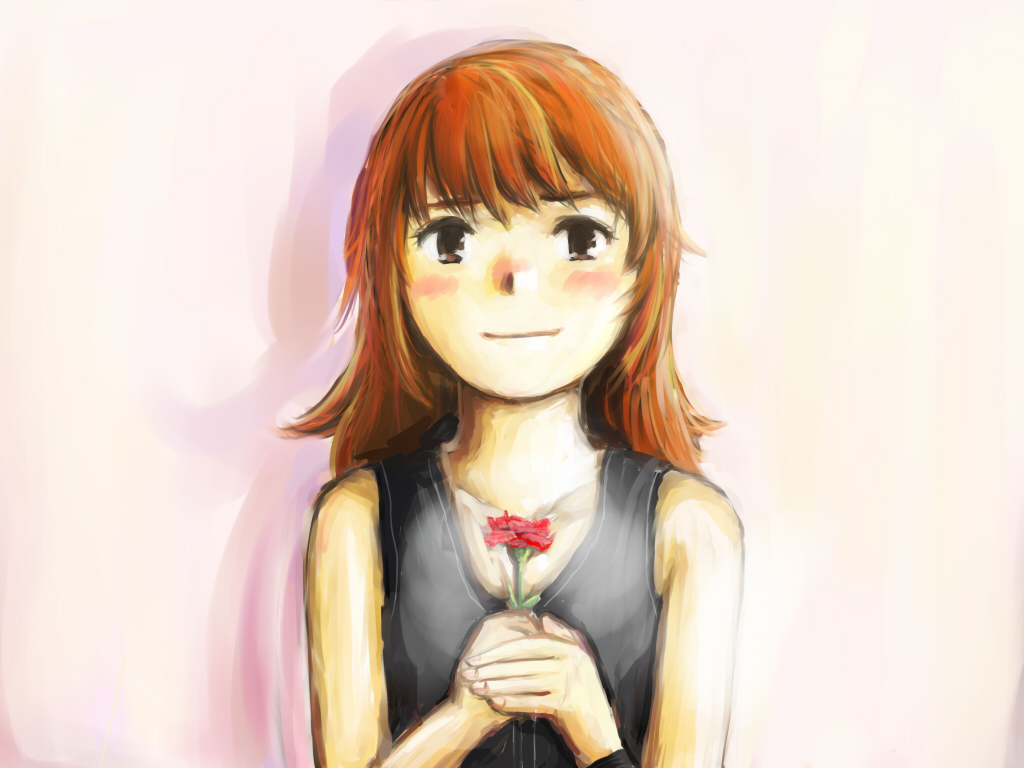2985
母の日に
- 2009-05-10T23:54:45
- とーり
透明に響く葵の言葉が耳にとまったのは、至極当然だったのかもしれない。
いつもみたいな眠気を誘う昼下がり。あの日は随分と、そう。自分でも意外なくらいに驚いてしまった。
「母の日?」
「せや。毎年贈り物はしとってんけど、せっかくやから今年は実家に帰ろうかおもてな。日曜日やし」
「なら私も帰ろうかな? ママ皆本さんみたいな若い男連れてこいって言ってたし」
葵はともかく紫穂が珍しく家のことを口にする。この前紹介された強烈なキャラをアタシは思い出した。
「うわ。相変わらず容赦無いな、紫穂のお母はん」
「裏表無いから♪」
「アンタのせいやろ! てか、皆本さん連れてくなんて許さへんで」
「えー」
「抜け駆け無しの約束やろ。せや、薫はどうすんねん?」
「え? あたし?」
「そ。どないすんの」
「あたし、は……」
不意に返答に詰まった。ここに残るとも実家に帰るとも、気軽に答えれば良かったろうに。その時なぜか唇がいうことを聞いてくれず、どうにか動いた口元はポッキーをぱつんと、あたしはソファーベッドに寝転がり天井を仰ぎ見る。笑顔の二人は変わらず、答えを待っていた。
〜母の日に〜
「どうしよっかな……」
ついため息をつく。買い物袋がやけに重い。二人には、あたしも会いに行くと答えておいた。答えておいて、いざどうしよか考えると、胸が詰まる。
失敗したなあ。そもそも普段なら葵が行くはずの買い物に出たのだって、じっくり考えたかったからだった。だのに、街は嫌みなくらい幸せそうな親子で溢れていた。
夕食の相談をしながらベビーカーを押す若い夫婦、仲良く買い物をするかしましい母娘、おじいさんの手を引く娘(中年のおばさんだけど)さん。形は違えどそれぞれが確かに親子で、すれ違うあたしを不意にいらとさせる。
「んと、頼まれたモノで忘れ物はない、と」
誰が見ている訳でもないのにわざと主張するように声を上げ周囲を確認してから、再び歩き始めた。そもそもあたしは、なんでこんなに戸惑っているのだろう。母さんに会いに行こうか考えているだけなのに。わざわざ母の日などと銘打ってくれているのだ、それくらいどうしたというのだろう。
『……女優の明石秋江さんが主演を努める……』
TVからアナウンサーの声が聞こえてきて、あたしはつい振り返る。夕暮れの街頭、古ぼけた小さなブラウン管に母さんの姿が映り、そしてアタシの姿が重なった。
新作の舞台が好評で連日大入り。もっと大勢の方に見てもらうために頑張りたい、と母さんはレポーターにはきはき答えている。
「そっか。嬉しいんだ、母さん」
舞台の成功を、母さんは芯から喜んでいる。そこは親子だ、作り笑顔かどうかは見れば分かる。例えTVを通じたものであっても。だけど、あたしの思ったことは母さんには届かない。もし届いたなら、母さんはどう言うだろうか。ショーウィンドに映ったアタシは、お世辞にも良い顔とは言えなかった。
続きは見ずに、また歩き出す。母さんの声はすぐ次のニュースを読み上げる声に押し流されていった。
「これが普通、なんだよなー」
小さい頃から母さんはあまり家にはいなかった。売れっ子女優なのだから、それは当たり前のことだった。そしてたまに喧嘩をすると、また母さんは家からいなくってしまった 。
「超度7」
右の手のひらをじっと見つめた。昔母さんの手を振り払おうとし、サイコキノで怪我をさせた手のひら。
強く握り込んで、また開く。そのまま金色に輝く空に向かって、雲をつかむように大きく伸ばす。あたしなら手が届くのに、母さんには決して届かない。呆れるくらいの絶対的な事実。
「……お見舞いには行かせてくれなかったな……」
それもまた、動かし様のない事実。あたしの心に傷が残るからと、母さんや好美姉ちゃんは言っていた。そのまま待っている方が、ずっとずっと辛かったのに。ごめんなさいと、謝らせて欲しかったのに。
手元からずり落ちかけた買い物袋を、ぎゅっと握り直す。
「だから、なのかな」
今の母さんとの距離。互いを傷つけることはない、ちょうど良い距離。昔出来なかった、させてもらえなかった記憶が、あたしの足を止めているんだろうか。だけど。会いに行くのが怖いのかと聞かれればそれは違う、と思う。
怖いのかもしれないけれど、そればかりでもない。
「母さんに会って甘えたい、のかな」
この年でそれはないな、つい苦笑いする。そもそも母の日なのに、あたしがなにかしてもらってどうするんだろう。
「……あ」
マンションに向かう足が止まる。影の伸びる歩道の真ん中で、あたしは立ちつくす。
『なにしてあげよっかなあ』
『私の場合はママがして欲しいこと言ってくれるから楽だけど』
葵と紫穂の言葉が頭をよぎる。
そうか。
そうだ。
そうなんだ。
気づいてしまえば、とても単純で、とても大切なこと。
「よっし!」
時間も随分経ってしまった。きっとお腹を空かせているだろう二人の元へ、あたしは駆けだしていく。パックで買った卵が割れないよう、こっそりサイコキノを使いながら。
☆☆☆☆☆
皆本のマンションに戻り、母の日には母さんに会いに行くと葵と紫穂に告げた。ふたりはさっきそう言ってたじゃないかとおかしな顔をしていたが、あたしは構わなかった。
その後ずっとニヤニヤしていたのがよほどおかしかったのか、帰ってきた皆本にまで熱があるのかなんて聞かれ、久々に吹き飛ばしたのはまあご愛敬という事にしておこう。というか思いたい。
「薫、あんたどないしたん?」
寝入りばな、ベッドで葵に聞かれた。気づけば紫穂もこちらに顔を向けている。なるほど、よほどあたしは妙な顔をしていたらしい。
「ん。大したことじゃないんだけどさ。ただ、二人の言ってた事を思い出して、わかったってだけ」
「全然わかんないんだけど」
紫穂が眉根を寄せる。こういうとき無理に『読もう』としないのは、紫穂なりの気遣いなのだろう。
「本当に大したことじゃないんだけどね……」
電気を落とした寝室の暗がり、ほのかな月明かりがカーテンの隙間から入るばかり。あたしは二人に、今日気づけた事をゆっくりと話しした。
「あたしが昔、家族とあんまりうまくいってなかったのは知ってるでしょ。だからかな。いつの間にか、してくれないしてくれないってばっかり思う様になっちゃってて」
「してあげる、って事に考えが回ってなかったんか」
「意外ね。薫ちゃん、あたし達や同じエスパーの事になると、あれだけ一生懸命なにかしてくれようとするのに」
家族だからこそだったかもしれない。母さんの事も好美ねーちゃんの事も大好きで、だけど、だからこそたった一人エスパーだった私と家族は、距離を縮めようとすればするほどお互いを傷つけた。あたしの癇癪で、何度か母さんを入院させてしまったこともある。
「ふたりのおかげだよ」
ありがとう、と言うと二人はこそばゆそうにぎこちない笑顔を見せた。
「応援……するっちゅうのも変な話やけどな」
「頑張ってね、薫ちゃん」
「うん」
それから。遠くに車の音が聞こえ変わらず月明かりがほのかに部屋を照らす中、しばらく二人といろんな事を話しして、いつの間にか寝入っていた。あれだけ話したのに、目覚めはとてもすっきりしていた。
☆☆☆☆☆
翌日、バベルに行く前にあたしは一人、久々に実家を訪れた。自分の家なのに帰ってくるじゃなく訪れると思ってるのに気づいて、ドアの前で苦笑いした。すぐにバベルからガードを兼ね派遣されている美人の管理人さんが出てきて、あたしを招き入れてくれた。
居間はとても整然としていた。母さんも好美ねーちゃんもあまり家にはいないけれど、はたきとブラシで管理人さんが丁寧に手入れしてくれている証拠だろう。二人とも遊び人然としてぶっきらぼうだから、掃除をしてくれる人が誰もいないと思うと少しぞっとする。あんまり人のこと言えないけどね。
「母さんの予定は、っと……」
すれ違いが多いせいか、母さんと好美ねーちゃんは壁掛けのローボードに自分の予定を書きつづるのが習慣になっている。五月十日、母の日は『舞台、午後一時入り』と綴ってある。
「やっぱりか」
成功している舞台だ。続演も決定したらしいし、きっと母さんも力が入っているのだろう。
どうしよう。予定表を前にして考え込む。例え当日帰りを待つにしても、何時になるのか分からない。舞台の打ち上げは毎回あるわけじゃないだろうけれど、あの年で未だ遊び盛りの母さんの事だ。何はなくとも多少遅くはなるだろう。
「うーん」
近くの椅子に座り、ぐるり見渡した。広々した居間には見目よく観葉植物や家具が並べられ、日の当たるフローリングには埃一つ無い。あまり生活臭のしない部屋でかすかに住人の存在を示すローボードを、私はまた見据えた。
「昔はこうだったな……」
バベルに預けられている時間はまだ良かった。高校生だった好美ねーちゃんもグラビアの仕事で忙しく、私は夕方一人でいることも多かった。ただただ母さんやねーちゃんの帰りを待って、葵や紫穂と一緒にやった落書き帳をまた開いたりして、ひどくつまらなかったのを思い出す。ようやく帰ってきた母さんに、遅いと文句を言うと、時折母さんは悲しそうな顔をしていた。
ついこの前の事のはずなのに、今のあたしにはずいぶん遠い世界の出来事にも感じるけれど、やっぱり、待つのはやっぱりつまらないものだ。
「あ、そっか!」
自分自身に確認するような大きな声。私は立ち上がり、そうだそうだと予定表の前で笑う。管理人さんが見れば、随分悪い顔をしていると言ったかもしれない。
「そうだよ。待つのはキライなんだ、あたし」
☆☆☆☆☆
「あーもーなんでここまで来てこうなるかなっ?!」
母さんの楽屋の前でうろうろうろうろ、何度も何度も通り過ぎては戻ってきて、怪しいことこの上ない。心なし、行き交うスタッフの人の顔も険しくなってきた気がする。
「いざとなるとこんななのかー、あたし。ホントに母さんの娘なんだろーか」
つい壁を背にして座り込む。バベルの任務では結構上手くやれてたつもりなんだけどな。激しい戦闘だってくぐり抜けてきたし。母さんみたいに大勢の前で舞台に上がったりするのとはまた別の緊張なんだろうけど、動揺してるのが自分でもよく分かる。
「やっぱり……怖いのかな」
驚いたような、困惑したような母さんの声は聞きたくない。よそよそしく、もしかすると慌ただしく応対されるのもたまらない。だからあれだけ考えて考えて、気持ちの整理はつけたはず。
だけど、わき上がってくる怖いって気持ちは間違いなくあたし自身の気持ち。それはどうしようもない。
「でも」
ここで踏みとどまっていても、何も出来ない。何も変わらない。なら。
「女は度胸!」
思い定めてドアの前に立つ。カーネーションを両手で胸の前にかざすと、不思議と気持ちが落ち着いていく。ちょっとだけ刺激的な香りを思い切り吸い込んで、もっと力をもらう。
笑ってもらいたい。
それだけかと他の人には言われるかもしれないけれど、それが母さんにしてあげたいこと。あたしには贅沢で高望みなのかもしれない、でも、だからあたしはドアをたたいた。おっかなびっくりに一度弱く、すぐに強く二度。母さんの返事が来る前に、無遠慮に開いた。
「……薫?」
「へへ、来ちゃった」
「どうしたの、突然」
舞台の前だ、台本を読み込んでいた母さんは不思議そうに目を見開く。
「はい!」
わざと不意を突くように背中に回した左手のカーネーションを、両の手で差し出した。母さんは一瞬空白の表情を浮かべ、やがて驚きを形作っていく。
「その、あの、さ。えと……ありがとう、母さん」
「……え? あ」
「今日、ほら。母の日」
照れくさくて恥ずかしくて、ぶっきらぼうに言葉を紡いだ。伝えたいことはたくさんあったのに、いざ母さんの前に出ると真っ白になっちゃって、母さんがゆっくり花を受け取るのをただ黙って見てた。
「……そっか。母の日、だったのね。そっか……あはは、やだ。気づきもしなかった」
そういうと母さんは、涙をこぼした。止めどなく溢れる涙が頬を濡らし床に落ち、あたしは少しだけ戸惑った。でもそこに、罪悪感は無かった。ごめんなさいと震え、好美姉ちゃんに言い訳してた昔と違い、喜びで胸が満たされていく。
「ありがとう、薫」
まだお化粧してなくて良かったわ。母さんはそれだけ言うとにっこり微笑んで、指で涙をゆっくりとぬぐった。
「……笑ってくれた」
小さく呟く。嬉しくて嬉しくて、自然あたしも笑顔になる。母さんもまた、豪奢な舞台衣装に身を包みながらも、この時ばかりは明石秋江ではない、見慣れた母さんの顔だった。
「……どうしたの?」
「あ、ううん。なんでもないの」
慌てて手を振って、照れくささを誤魔化す。でも誤魔化しきれなかった分が、口をついて言葉になった。
「あのね、母さん」
「なあに」
母さんは笑顔で聞き返す。
「……ごめんね」
「なにが?」
ゆっくり母さんは言う。
「昔、たくさん苦労かけて。あたし、ずっと謝りたいって思ってた」
「……あ」
母さんの表情が陰る。悲しそうでつらそうに口元を引き絞った母さん。アタシは改めて続けた。
「ごめんね」
「……ううん、いいのよ」
母さんの切ない声がとても痛かった。だけど、ずっと胸につかえていたことがどんどんあふれ出していく。
「あたし、ずっと母さんもねーちゃんも何もしてくれないって思ってた」
「……そう」
「だけどね、そうじゃないんだって。あたしがなにかしてあげたいんだって、そう思ったの。そう思えたのは、周りの人たちのおかげ。皆本の、紫穂の、葵の、局長の、朧さんの、バベルの、クラスのみんなの……」
すっと息つぎをして、伝えた。
「好美ねーちゃんの、母さんのおかげ。あたしを放り出さずに、なんとかしようとしてくれた人たちのおかげ」
「……薫」
「普通の子だったら良かったんだろうけど。超度7なんてやっかいな能力を持って拗ねてひねてたあたしは、母さん泣かしてばかりだった。出来るはずもないのに、本気で喧嘩してくれないっていじけてたけど」
言いかけて、母さんがあたしを抱きしめる。柔らかい胸元の、とても甘く懐かしい香りを感じながら、続けた。
「今は、自分の超能力 が好きになれた。笑えるようになった。だからね、あたし、嬉しいんだ。あたしが、母さんを笑わせてあげられたから。今日、母さんが笑ってくれたから」
泣かせちゃったけど、感じるのはあの時みたいな後悔じゃなくて喜び。誰にも抱きしめてもらえなかった寂しさじゃなくて、暖かな優しさ。
「……そう」
頭を撫で、髪を梳く母さんの手がとても心地よい。
「母さん」
「なに?」
「今日、早くあがれる?」
どうして、と母さんが耳元でささやく。でも纏った明るい彩りは決して隠せるものではなく。
「プレゼント用意してあるんだ。だからさ、今日はウチで。好美ねーちゃんも来れるって」
「それで母さんが行かなかったら、私が悪者じゃない」
「そーだね」
「もう! ずるい子ね、全く」
母さんが声を上げて、笑う。あたしもつられて、くすくす笑った。
「だって、あたし。もう大人だもん」
ホントにね、と母さんが言って。こんなにも大きくなって、ともう一度言って。髪を梳かれながら、舞台の幕が開くもうほんのちょっとの間だけ、母さんと一緒の時間を過ごした。
いつもみたいな眠気を誘う昼下がり。あの日は随分と、そう。自分でも意外なくらいに驚いてしまった。
「母の日?」
「せや。毎年贈り物はしとってんけど、せっかくやから今年は実家に帰ろうかおもてな。日曜日やし」
「なら私も帰ろうかな? ママ皆本さんみたいな若い男連れてこいって言ってたし」
葵はともかく紫穂が珍しく家のことを口にする。この前紹介された強烈なキャラをアタシは思い出した。
「うわ。相変わらず容赦無いな、紫穂のお母はん」
「裏表無いから♪」
「アンタのせいやろ! てか、皆本さん連れてくなんて許さへんで」
「えー」
「抜け駆け無しの約束やろ。せや、薫はどうすんねん?」
「え? あたし?」
「そ。どないすんの」
「あたし、は……」
不意に返答に詰まった。ここに残るとも実家に帰るとも、気軽に答えれば良かったろうに。その時なぜか唇がいうことを聞いてくれず、どうにか動いた口元はポッキーをぱつんと、あたしはソファーベッドに寝転がり天井を仰ぎ見る。笑顔の二人は変わらず、答えを待っていた。
〜母の日に〜
「どうしよっかな……」
ついため息をつく。買い物袋がやけに重い。二人には、あたしも会いに行くと答えておいた。答えておいて、いざどうしよか考えると、胸が詰まる。
失敗したなあ。そもそも普段なら葵が行くはずの買い物に出たのだって、じっくり考えたかったからだった。だのに、街は嫌みなくらい幸せそうな親子で溢れていた。
夕食の相談をしながらベビーカーを押す若い夫婦、仲良く買い物をするかしましい母娘、おじいさんの手を引く娘(中年のおばさんだけど)さん。形は違えどそれぞれが確かに親子で、すれ違うあたしを不意にいらとさせる。
「んと、頼まれたモノで忘れ物はない、と」
誰が見ている訳でもないのにわざと主張するように声を上げ周囲を確認してから、再び歩き始めた。そもそもあたしは、なんでこんなに戸惑っているのだろう。母さんに会いに行こうか考えているだけなのに。わざわざ母の日などと銘打ってくれているのだ、それくらいどうしたというのだろう。
『……女優の明石秋江さんが主演を努める……』
TVからアナウンサーの声が聞こえてきて、あたしはつい振り返る。夕暮れの街頭、古ぼけた小さなブラウン管に母さんの姿が映り、そしてアタシの姿が重なった。
新作の舞台が好評で連日大入り。もっと大勢の方に見てもらうために頑張りたい、と母さんはレポーターにはきはき答えている。
「そっか。嬉しいんだ、母さん」
舞台の成功を、母さんは芯から喜んでいる。そこは親子だ、作り笑顔かどうかは見れば分かる。例えTVを通じたものであっても。だけど、あたしの思ったことは母さんには届かない。もし届いたなら、母さんはどう言うだろうか。ショーウィンドに映ったアタシは、お世辞にも良い顔とは言えなかった。
続きは見ずに、また歩き出す。母さんの声はすぐ次のニュースを読み上げる声に押し流されていった。
「これが普通、なんだよなー」
小さい頃から母さんはあまり家にはいなかった。売れっ子女優なのだから、それは当たり前のことだった。そしてたまに喧嘩をすると、また母さんは家から
「超度7」
右の手のひらをじっと見つめた。昔母さんの手を振り払おうとし、サイコキノで怪我をさせた手のひら。
強く握り込んで、また開く。そのまま金色に輝く空に向かって、雲をつかむように大きく伸ばす。あたしなら手が届くのに、母さんには決して届かない。呆れるくらいの絶対的な事実。
「……お見舞いには行かせてくれなかったな……」
それもまた、動かし様のない事実。あたしの心に傷が残るからと、母さんや好美姉ちゃんは言っていた。そのまま待っている方が、ずっとずっと辛かったのに。ごめんなさいと、謝らせて欲しかったのに。
手元からずり落ちかけた買い物袋を、ぎゅっと握り直す。
「だから、なのかな」
今の母さんとの距離。互いを傷つけることはない、ちょうど良い距離。昔出来なかった、させてもらえなかった記憶が、あたしの足を止めているんだろうか。だけど。会いに行くのが怖いのかと聞かれればそれは違う、と思う。
怖いのかもしれないけれど、そればかりでもない。
「母さんに会って甘えたい、のかな」
この年でそれはないな、つい苦笑いする。そもそも母の日なのに、あたしがなにかしてもらってどうするんだろう。
「……あ」
マンションに向かう足が止まる。影の伸びる歩道の真ん中で、あたしは立ちつくす。
『なにしてあげよっかなあ』
『私の場合はママがして欲しいこと言ってくれるから楽だけど』
葵と紫穂の言葉が頭をよぎる。
そうか。
そうだ。
そうなんだ。
気づいてしまえば、とても単純で、とても大切なこと。
「よっし!」
時間も随分経ってしまった。きっとお腹を空かせているだろう二人の元へ、あたしは駆けだしていく。パックで買った卵が割れないよう、こっそりサイコキノを使いながら。
☆☆☆☆☆
皆本のマンションに戻り、母の日には母さんに会いに行くと葵と紫穂に告げた。ふたりはさっきそう言ってたじゃないかとおかしな顔をしていたが、あたしは構わなかった。
その後ずっとニヤニヤしていたのがよほどおかしかったのか、帰ってきた皆本にまで熱があるのかなんて聞かれ、久々に吹き飛ばしたのはまあご愛敬という事にしておこう。というか思いたい。
「薫、あんたどないしたん?」
寝入りばな、ベッドで葵に聞かれた。気づけば紫穂もこちらに顔を向けている。なるほど、よほどあたしは妙な顔をしていたらしい。
「ん。大したことじゃないんだけどさ。ただ、二人の言ってた事を思い出して、わかったってだけ」
「全然わかんないんだけど」
紫穂が眉根を寄せる。こういうとき無理に『読もう』としないのは、紫穂なりの気遣いなのだろう。
「本当に大したことじゃないんだけどね……」
電気を落とした寝室の暗がり、ほのかな月明かりがカーテンの隙間から入るばかり。あたしは二人に、今日気づけた事をゆっくりと話しした。
「あたしが昔、家族とあんまりうまくいってなかったのは知ってるでしょ。だからかな。いつの間にか、してくれないしてくれないってばっかり思う様になっちゃってて」
「してあげる、って事に考えが回ってなかったんか」
「意外ね。薫ちゃん、あたし達や同じエスパーの事になると、あれだけ一生懸命なにかしてくれようとするのに」
家族だからこそだったかもしれない。母さんの事も好美ねーちゃんの事も大好きで、だけど、だからこそたった一人エスパーだった私と家族は、距離を縮めようとすればするほどお互いを傷つけた。あたしの癇癪で、何度か母さんを入院させてしまったこともある。
「ふたりのおかげだよ」
ありがとう、と言うと二人はこそばゆそうにぎこちない笑顔を見せた。
「応援……するっちゅうのも変な話やけどな」
「頑張ってね、薫ちゃん」
「うん」
それから。遠くに車の音が聞こえ変わらず月明かりがほのかに部屋を照らす中、しばらく二人といろんな事を話しして、いつの間にか寝入っていた。あれだけ話したのに、目覚めはとてもすっきりしていた。
☆☆☆☆☆
翌日、バベルに行く前にあたしは一人、久々に実家を訪れた。自分の家なのに帰ってくるじゃなく訪れると思ってるのに気づいて、ドアの前で苦笑いした。すぐにバベルからガードを兼ね派遣されている美人の管理人さんが出てきて、あたしを招き入れてくれた。
居間はとても整然としていた。母さんも好美ねーちゃんもあまり家にはいないけれど、はたきとブラシで管理人さんが丁寧に手入れしてくれている証拠だろう。二人とも遊び人然としてぶっきらぼうだから、掃除をしてくれる人が誰もいないと思うと少しぞっとする。あんまり人のこと言えないけどね。
「母さんの予定は、っと……」
すれ違いが多いせいか、母さんと好美ねーちゃんは壁掛けのローボードに自分の予定を書きつづるのが習慣になっている。五月十日、母の日は『舞台、午後一時入り』と綴ってある。
「やっぱりか」
成功している舞台だ。続演も決定したらしいし、きっと母さんも力が入っているのだろう。
どうしよう。予定表を前にして考え込む。例え当日帰りを待つにしても、何時になるのか分からない。舞台の打ち上げは毎回あるわけじゃないだろうけれど、あの年で未だ遊び盛りの母さんの事だ。何はなくとも多少遅くはなるだろう。
「うーん」
近くの椅子に座り、ぐるり見渡した。広々した居間には見目よく観葉植物や家具が並べられ、日の当たるフローリングには埃一つ無い。あまり生活臭のしない部屋でかすかに住人の存在を示すローボードを、私はまた見据えた。
「昔はこうだったな……」
バベルに預けられている時間はまだ良かった。高校生だった好美ねーちゃんもグラビアの仕事で忙しく、私は夕方一人でいることも多かった。ただただ母さんやねーちゃんの帰りを待って、葵や紫穂と一緒にやった落書き帳をまた開いたりして、ひどくつまらなかったのを思い出す。ようやく帰ってきた母さんに、遅いと文句を言うと、時折母さんは悲しそうな顔をしていた。
ついこの前の事のはずなのに、今のあたしにはずいぶん遠い世界の出来事にも感じるけれど、やっぱり、待つのはやっぱりつまらないものだ。
「あ、そっか!」
自分自身に確認するような大きな声。私は立ち上がり、そうだそうだと予定表の前で笑う。管理人さんが見れば、随分悪い顔をしていると言ったかもしれない。
「そうだよ。待つのはキライなんだ、あたし」
☆☆☆☆☆
「あーもーなんでここまで来てこうなるかなっ?!」
母さんの楽屋の前でうろうろうろうろ、何度も何度も通り過ぎては戻ってきて、怪しいことこの上ない。心なし、行き交うスタッフの人の顔も険しくなってきた気がする。
「いざとなるとこんななのかー、あたし。ホントに母さんの娘なんだろーか」
つい壁を背にして座り込む。バベルの任務では結構上手くやれてたつもりなんだけどな。激しい戦闘だってくぐり抜けてきたし。母さんみたいに大勢の前で舞台に上がったりするのとはまた別の緊張なんだろうけど、動揺してるのが自分でもよく分かる。
「やっぱり……怖いのかな」
驚いたような、困惑したような母さんの声は聞きたくない。よそよそしく、もしかすると慌ただしく応対されるのもたまらない。だからあれだけ考えて考えて、気持ちの整理はつけたはず。
だけど、わき上がってくる怖いって気持ちは間違いなくあたし自身の気持ち。それはどうしようもない。
「でも」
ここで踏みとどまっていても、何も出来ない。何も変わらない。なら。
「女は度胸!」
思い定めてドアの前に立つ。カーネーションを両手で胸の前にかざすと、不思議と気持ちが落ち着いていく。ちょっとだけ刺激的な香りを思い切り吸い込んで、もっと力をもらう。
笑ってもらいたい。
それだけかと他の人には言われるかもしれないけれど、それが母さんにしてあげたいこと。あたしには贅沢で高望みなのかもしれない、でも、だからあたしはドアをたたいた。おっかなびっくりに一度弱く、すぐに強く二度。母さんの返事が来る前に、無遠慮に開いた。
「……薫?」
「へへ、来ちゃった」
「どうしたの、突然」
舞台の前だ、台本を読み込んでいた母さんは不思議そうに目を見開く。
「はい!」
わざと不意を突くように背中に回した左手のカーネーションを、両の手で差し出した。母さんは一瞬空白の表情を浮かべ、やがて驚きを形作っていく。
「その、あの、さ。えと……ありがとう、母さん」
「……え? あ」
「今日、ほら。母の日」
照れくさくて恥ずかしくて、ぶっきらぼうに言葉を紡いだ。伝えたいことはたくさんあったのに、いざ母さんの前に出ると真っ白になっちゃって、母さんがゆっくり花を受け取るのをただ黙って見てた。
「……そっか。母の日、だったのね。そっか……あはは、やだ。気づきもしなかった」
そういうと母さんは、涙をこぼした。止めどなく溢れる涙が頬を濡らし床に落ち、あたしは少しだけ戸惑った。でもそこに、罪悪感は無かった。ごめんなさいと震え、好美姉ちゃんに言い訳してた昔と違い、喜びで胸が満たされていく。
「ありがとう、薫」
まだお化粧してなくて良かったわ。母さんはそれだけ言うとにっこり微笑んで、指で涙をゆっくりとぬぐった。
「……笑ってくれた」
小さく呟く。嬉しくて嬉しくて、自然あたしも笑顔になる。母さんもまた、豪奢な舞台衣装に身を包みながらも、この時ばかりは明石秋江ではない、見慣れた母さんの顔だった。
「……どうしたの?」
「あ、ううん。なんでもないの」
慌てて手を振って、照れくささを誤魔化す。でも誤魔化しきれなかった分が、口をついて言葉になった。
「あのね、母さん」
「なあに」
母さんは笑顔で聞き返す。
「……ごめんね」
「なにが?」
ゆっくり母さんは言う。
「昔、たくさん苦労かけて。あたし、ずっと謝りたいって思ってた」
「……あ」
母さんの表情が陰る。悲しそうでつらそうに口元を引き絞った母さん。アタシは改めて続けた。
「ごめんね」
「……ううん、いいのよ」
母さんの切ない声がとても痛かった。だけど、ずっと胸につかえていたことがどんどんあふれ出していく。
「あたし、ずっと母さんもねーちゃんも何もしてくれないって思ってた」
「……そう」
「だけどね、そうじゃないんだって。あたしがなにかしてあげたいんだって、そう思ったの。そう思えたのは、周りの人たちのおかげ。皆本の、紫穂の、葵の、局長の、朧さんの、バベルの、クラスのみんなの……」
すっと息つぎをして、伝えた。
「好美ねーちゃんの、母さんのおかげ。あたしを放り出さずに、なんとかしようとしてくれた人たちのおかげ」
「……薫」
「普通の子だったら良かったんだろうけど。超度7なんてやっかいな能力を持って拗ねてひねてたあたしは、母さん泣かしてばかりだった。出来るはずもないのに、本気で喧嘩してくれないっていじけてたけど」
言いかけて、母さんがあたしを抱きしめる。柔らかい胸元の、とても甘く懐かしい香りを感じながら、続けた。
「今は、自分の
泣かせちゃったけど、感じるのはあの時みたいな後悔じゃなくて喜び。誰にも抱きしめてもらえなかった寂しさじゃなくて、暖かな優しさ。
「……そう」
頭を撫で、髪を梳く母さんの手がとても心地よい。
「母さん」
「なに?」
「今日、早くあがれる?」
どうして、と母さんが耳元でささやく。でも纏った明るい彩りは決して隠せるものではなく。
「プレゼント用意してあるんだ。だからさ、今日はウチで。好美ねーちゃんも来れるって」
「それで母さんが行かなかったら、私が悪者じゃない」
「そーだね」
「もう! ずるい子ね、全く」
母さんが声を上げて、笑う。あたしもつられて、くすくす笑った。
「だって、あたし。もう大人だもん」
ホントにね、と母さんが言って。こんなにも大きくなって、ともう一度言って。髪を梳かれながら、舞台の幕が開くもうほんのちょっとの間だけ、母さんと一緒の時間を過ごした。
Please don't use this texts&images without permission of とーり.
こんにちは、とーりです。
今回は絵師様であるトキコさんのイラストにびびっと来まして、母の日に間に合うようSSにしたためてみました(残りわずか5分ですがorz)
挿絵の使用許可、またわざわざ私服バージョンを用意してくださったトキコ様に感謝いたします。
読者様にはどのように受け止められたでしょうか。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますです(^^
今回は絵師様であるトキコさんのイラストにびびっと来まして、母の日に間に合うようSSにしたためてみました(残りわずか5分ですがorz)
挿絵の使用許可、またわざわざ私服バージョンを用意してくださったトキコ様に感謝いたします。
読者様にはどのように受け止められたでしょうか。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますです(^^
[mente]
作品の感想を投稿、閲覧する -> [reply]